DX推進ニーズやIT人材の不足を背景に、企業のパートナーとして需要が高まっているSIer。市場ではシステムエンジニアの求人ニーズは依然として高く、2023年のdodaによる調査結果では、転職求人倍率が10倍を超えるほどになっています。(※1)。
とはいえノーコード・ローコード開発、クラウドサービスの普及により、簡易なシステム開発や運用・保守を内製化する企業は増加傾向にあります。今後のSIerにはテクノロジーの発展やトレンドの変化、新たに顕在化した課題を踏まえた、さらなる「進化」が期待されています。
この記事では、そんなSIerのトレンドや将来像を踏まえつつ、ソルクシーズの経営戦略についてレポートします。将来性のあるSIerへの転職・就職を検討している方は、ぜひ最後までご一読ください。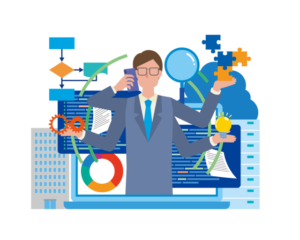
先端テクノロジーの活用
現在SIのトレンドとして挙げられるのは、AI、ビッグデータ、クラウド、FinTechといった先端テクノロジーの活用です。
企業がDXを推進して競争力を向上していくためには、先端テクノロジーの導入が欠かせません。
例えば老朽化した基幹システム・業務システムを刷新する場合、新規システムを構築する場合にも、クラウドやパッケージソフト、セキュリティなどに関する詳細な知識は必須です。また、業務を効率化するために、AIやRPAを導入する企業も増えています。
予測しづらい昨今の市場に対応するためには、データに基づく迅速な経営判断が重要です。そのための仕組みを社内に構築して運用するためには、高度なデータサイエンスの知識・スキルが必要になります。
さらに、競合他社に対する競争優位性を高めるうえでは、顧客ニーズに応えるサービスのデジタル化や新たなビジネスモデルの構築など、攻めのDX推進も不可欠。AI・IoT・自動化・FinTechなど、複数の技術を組み合わせたサービスの開発が求められるでしょう。
しかしそれぞれの技術に関する知見やノウハウがあるIT人材は慢性的な不足が続いており、内製化はますます難しくなっています。経済産業省の試算でも、2030年に従来型IT人材が約10万人余剰し、「先端IT人材」は約55万人不足するシナリオ予測があります。(※2)。
そのため、これらの技術に関する知見を蓄積しているSIerや、先端IT人材が多数在籍しているSIer、社内に先端IT人材を育成するノウハウが整っているSIerは、今後さらなる成長が見込まれます。
そのようなSIerは、システムエンジニアやインフラエンジニアの採用においても強みを訴求しやすく、結果として優秀な人材を獲得できるという好循環につながるでしょう。
業界ごとのノウハウやサービス提供
特定業界のシステム開発・運用ノウハウを活かした専門的なサービスの提供も、今後ニーズが高まっていく可能性の高いSIerの役割です。
現在は金融業界・官公庁・製造業・医療業界などで、業界固有のワークフローや課題をふまえたシステム開発や、ITインフラ構築の案件、DX推進・サービス導入・開発組織改善などが求められています。
これらの業界ではユーザビリティの向上に加えて、保守やセキュリティなどの観点から高い安全性と信頼性を担保することが欠かせません。先端技術への関心度が高く、潤沢なコストをIT投資に注入する傾向にあるため、大規模なプロジェクトを獲得しやすい領域といえるでしょう。
特に金融業界・官公庁は法規制への細かい対応が求められるため、長期的な運用保守の案件につながりやすいのが特徴です。マイナンバー制度・電子政府・電子自治体なども、案件拡大につながる動向といえます。
競争が激化している領域ではあるものの、すでに業界内での実績が豊富で高い専門性・信頼性を有しているSIerや、技術力が高く大規模プロジェクトに対応できるSIerの需要は拡大しています。
とくに業界固有のワークフローやビジネス上の課題・法規制等の要件にくわしく、積極的な提案を行えるSIerは、顧客からの信頼と新規・継続の受注を得やすいでしょう。専門性を高めて多くの案件を獲得できれば、さらなるノウハウの蓄積によって競合他社との差別化を推進できます。
上流工程の実績とノウハウ
SIer業界で以前から問題とされていた「多重下請構造」から脱却できるかどうかも、将来性に直結するテーマです。多重下請構造とは、システム開発・インフラ構築などの案件を受注した大手企業が、業務の大半を下請会社に委託する構造を指します。
受注案件に二次請け・三次請けが多くなるほどキャリアアップに必要な上流工程の経験ができないため、社内にスキル・ノウハウが蓄積されません。結果として、すでに上流工程の実績が豊富な企業に案件が集中しやすく、業界格差が広がっています。
昨今は業界構造改善のために、下請企業への委託を行わず、システム開発の多くの工程を社内で完結するSIerもあります。上流工程に関われるSIerなら、金融業界・官公庁などの大規模プロジェクトに一気通貫で携わることで、ノウハウも社内に蓄積されます。
これらの理由から、上流工程の実績・ノウハウがあるかどうかは、SIerの将来性を評価する指標として重要になっていくでしょう。特に規模の大きいプロジェクトを完遂するためには、予算・リソース・進捗の管理やリスクヘッジ、パートナー企業を統率するリーダーシップなど、高度なプロジェクトマネジメントの体制が欠かせません。
今後は、プロジェクトマネジメントのスキルを保有する人材の採用・育成が事業の成長を左右するキーポイントになるでしょう。2023年にLinkedInが公開した「日本で今、需要の高いスキル」でも、マネジメントスキルは3位に選出されています(※3)。
強みを活かした自社サービスの開発
SIビジネスだけでなく、自社サービスの開発・展開を行っているSIerも将来性が期待できます。
収益源が増えることで経営が安定しやすいのはもちろん、最新技術のノウハウの蓄積や新規の顧客獲得にもつながり、SIビジネスとの相乗効果で競争優位性を獲得できます。自由度の高さや得られる経験・知識の幅広さから、自社サービス開発関連の求人はエンジニアの注目を集めやすくなっています。
これらの観点も含めて、現在とくに注目度が高まっているのが、先端IT技術を活用したソリューションです。たとえばクラウドやAI・IoT・FinTechなどの技術を駆使して業界固有の課題を解決するサービスの展開には、多くのビジネスチャンスがあるでしょう。
さらに、国内だけではなく海外に自社サービスを展開するケースも徐々に広がっています。そもそも、SIビジネスは日本独自の進化を遂げてきており、海外はシステム開発から運用・保守までを一貫してアウトソースする文化はありません。そのため海外進出がしにくく、国内市場に依存してしまうというSIerの課題がありました。
その点、自社サービスであれば、海外の市場・ニーズを視野に入れたサービス開発が可能です。成長させることができれば、国内の市場動向や景気の変動に経営を左右されにくくなり、より安定した事業基盤を築くことができるでしょう。
働き方改革・人材育成の推進
今後は先端IT人材が慢性的に不足していくため、優秀なエンジニアが「ここで働きたい」と思える会社であるかどうかも競争力を大きく左右するポイントになります。
これまで以上に重要になってくるのが労働環境の改善です。働き方改革やキャリアの多様性を推進する姿勢がますます求められるようになるでしょう。有給休暇・産休・育休といった福利厚生の充実、テレワーク・リモートワークやフレックスタイム制などの導入、残業を減らすための業務効率化などの取り組みが重要です。
また、エンジニアとして成長できる案件の豊富さや研修制度・学習プログラムの充実度を重視する人材も少なくありません。
従業員満足度を高めて企業イメージを向上させるこれらの取り組みは、採用だけでなく、クライアントや株主といったステークホルダーからの評価にもつながります。
DXで日本のビジネスを導く「ソルクシーズ」の成長戦略
このように時代に即した進化が求められているSIerですが、ソルクシーズグループもさらなる成長を見据えて、SIビジネスと自社サービスの両輪でさまざまな取り組みを推進しています。
成長戦略のひとつは「専門店化」。金融・官公庁・製造業・自動車業界など、特定の業界や領域に強いグループ企業によって、非価格競争力の強化に取り組んでいます。
例えばエクスモーションは、組込みソフトウェア開発に特化したコンサルティングファームです。自動車業界をはじめとした機器の組込み分野に強みがあり、DX支援のノウハウ・実績を蓄積。2023年には業務提携やM&Aによる事業規模拡大にも着手しました。
ソルクシーズとしては、かねてからの得意分野である金融業界のシステム開発も好調で、ブロックチェーンなど先端技術を活用した案件にも携わっており、知見を蓄積しています。
グループ全体を見渡すと、「企業向けオンラインストレージ」「個別クレジットシステム」「自動車教習所向けの各種ソリューション」「製造業の工場の生産性を高める状態監視/予知保全システム」「医療・介護業界の施設利用者の見守りサービス」「生成AI支援サービス」などの自社サービスが順調に顧客を拡大しています。ベトナムで教習所事業を展開するなど、ASEAN+3のマーケットにもサービスを展開中です。
IoT(IIoT)・組込・制御・計測関連のソリューションに特化したイー・アイ・ソルでは、航空宇宙・防衛領域にマーケットを拡大。2024年5月にアメリカテキサス州で開催された「NI Connect 2024」では、Asia / Pacificの企業約300社のうち、日本では唯一となるOutstanding Contribution Awardを受賞しました。
今後はこれらのストック型ビジネスやコンサルティングサービスの比率を高めることで、より安定した収益基盤の構築をめざしていきます。
さらに近年は、人材育成にも注力しています。階層別研修やスキルアップ勉強会、外部教育機関など、多岐にわたるプログラムを実施。独自に運営するオンライン教育プログラム「SOLXYZ Academy」は、言語や環境・データベースなど16分類で50以上のコースがあり、現場のニーズにマッチしたリスキリングができます。2022年にはライブ動画学習サービス「Schoo」も、全社員に無料開放しました。
エンジニアが働きやすい環境を目指して、長時間労働の削減やテレワークの導入、フリーアドレス制オフィスの整備、福利厚生の改革も推進中。平均残業時間は6.7時間と、SEの平均である32.8時間を大きく下回っています。人間関係や風通しが良い社風のため、3年離職率8.6%、平均勤続年数14年と定着率も高く、従業員満足度が高い会社です(※4)。
事業・サービスと採用・育成における多様な取り組みが功を奏し、2024年12月期第2四半期にはグループ全体で受注状況が過去最高水準を達成。新卒採用者数も、過去最高を記録しました。ソルクシーズグループはさらなる進化をめざし、今後も挑戦を続けていきます。将来性の高いSIerで働きたいとお考えの方は、ぜひソルクシーズの採用情報をチェックしてみてください。
出典
※1:doda転職求人倍率レポート(2023年7月発行版)|doda中途採用をお考えの法人様へ
パーソルキャリア株式会社 転職サービス「doda(デューダ)」
https://www.saiyo-doda.jp/report/12323
※2:- IT 人材需給に関する調査 -
みずほ情報総研株式会社(経済産業省委託事業)
「IT需要の伸び」:中位、「生産性の上昇率」:0.7%、Reスキル率:1.0%固定の場合の試算
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf?_fsi=EeSW2thF
※3:【LinkedIn独自調査】「日本で今、最も需要の高いスキル」トップ10を発表
LinkedIn
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000066809.html?_fsi=EeSW2thF
※4:ソルクシーズのカルチャー&福利厚生 | 株式会社ソルクシーズ|solxyz
株式会社ソルクシーズ
https://www.solxyz.co.jp/newgraduate/aboutus/culture/
※この記事は2025年01月23日に公開した記事を再編集しています。



