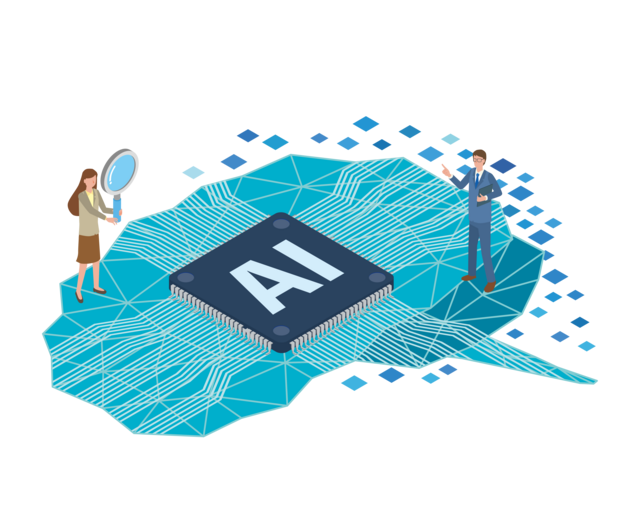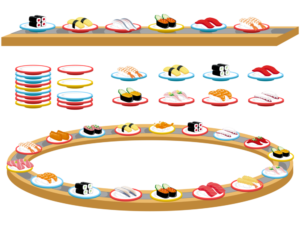AI技術の進化に伴い、LLM(大規模言語モデル)を活用したAIサービスやシステムが数多くリリースされています。LLMは大量のデータセットを利用した学習と高度なディープラーニングの技術により、自然言語を活用したやり取りやさまざまな処理を実現できる技術です。
従来のAI技術と比べてLLMが革新的だったのが、高度な言語理解の能力です。ユーザーが入力したテキストなどの言語情報を適切に把握して、違和感のないレスポンスを提供することができます。これにより、人間同士で会話をするような、直感的かつスムーズなAI活用が可能になりました。
ソルクシーズもLLMの活用を進めており、2024年10月には、社内向けAIシステム「SOLXYZ Assistant」の運用をスタートしています。この記事では、LMMを活用したサービスについて解説したうえで、「SOLXYZ Assistant」の目的と実現できることを、「PR TIMES STORY」に掲載された開発者インタビューの内容も交えつつ紹介していきます。
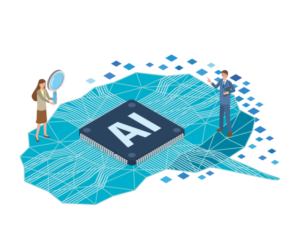
LLMを活用したサービスとLLMの課題
LLMを用いた代表的なサービスとして、まず挙げられるのがAIによる検索や情報収集です。
AIとチャットをする感覚で情報収集や検索結果の要約・翻訳ができるため、検索プラットフォームに比べて感覚的・効率的なリサーチが可能になりました。膨大なサイトから情報を探さなくても、ピンポイントの質問で即座に回答が得られる柔軟性の高さも強みといえます。
難解・専門的なテキストをわかりやすい言葉に変換したり、資格試験に対応するオリジナルの問題集を作成したり、要素・キーワードを抽出して分類・図化したり、市場調査のためのフレームワークを実行したりと、多様な場面での活用が可能です。
最近は音声・画像を入力できるサービスも登場しており、画像分析など幅広い用途での利用が可能になっています。
例えば、これらの機能をカスタマーサポートの部署で導入すれば、AIの自動応答による人件費削減や、24時間対応による顧客満足度の向上も期待できるでしょう。今後は、製品が故障した際に、ユーザーが送付した写真を分析して原因特定を行うといったソリューションも生まれるかもしれません。AIによる感情分析の技術も進化しており、より顧客・ユーザーに寄り添った対応も可能になりつつあります。
音声入力の機能を使って、ミーティングの議事録を作成することも可能です。リアルタイムで論点や複数の意見をまとめるなど、円滑な議論・コミュニケーションにも便利です。
ビジネスシーンでは、文書や資料の作成、画像生成などの用途が増えています。形式や目的・概要・文体などを指示するだけで文章・文書を出力してくれるため、大幅な業務効率化につながります。「入力した内容の続きを考えてもらう」「別な言葉に言い換えてもらう」といった使い方も可能です。
画像生成もLLMを活かせる領域のひとつです。テキストで指示するだけで、写真・イラスト・ロゴマークなど多様な画像を生成できるので、広告出稿・コンテンツ作成の手間やコストの削減を実現できます。
プログラミングの領域でも、簡単なコードの生成やバグチェックはAIに任せることができ、システムエンジニアのリソースをより創造的な業務に投入できます。
ビジネスアイデアや改善案などの検討でもLLMが使えます。ECサイトの商品情報をAIが分析して、出品者に改善提案を実施するサービスも生まれています。
このように幅広い用途で使えるLLMですが、入力した機密情報・個人情報がAIに学習されることで、社外に漏洩してしまうリスクもゼロではありません。
例えばプロンプトインジェクションは、悪意のある利用者が巧妙・特殊な入力を行うことで、システム側の意図していない動作・出力を引き起こす攻撃手法。これにより、企業の情報が外部流出してしまう危険性があります。もちろん、不正アクセスやサイバー攻撃などのリスクも無視できません。
LLMを活用したサービスを導入する際は、これらのリスクを認識することとセキュリティ対策が不可欠です。
加えて、参照情報の範囲が限定的なところも、LLMを活用したサービスの弱点といえるでしょう。LLMのアウトプットは、あらかじめ学習した膨大なデータを参照して生成されます。
不特定多数のユーザーを想定するほとんどのサービスでは、インターネット上の情報など、広く公開されている情報をこの学習データに利用しています。そのため、幅広いニーズに対応できる反面、学習時点で公開されていない最新情報や、特定の分野・業界・企業に固有のニッチな情報に関しては、適切な回答を得られないケースも少なくありません。
ハルシネーションも、LLMにつきまとう問題のひとつです。ハルシネーションとは、事実とは異なる回答を、LLMがさも事実であるかのように出力する現象。原因として、学習データそのものに偏りや曖昧さ、誤りが含まれている場合のほかに、AIモデルそのものの構造的な問題も指摘されています。
ユーザーは回答内容の信憑性を判断しながらLLMサービスを利用しないと、フェイクニュースを発信してしまう恐れがあります。企業としての発信であれば、社会的な信用やブランドイメージが損なわれるリスクもあるでしょう。
このような課題を背景に、「責任あるAI」というキーワードが注目されるようになりました。昨今はサービス提供者側にも、LLMやLLMが出力する情報のセキュリティ・安全性・公平性・透明性に関する考慮が求められています。
「SOLXYZ Assistant」開発の経緯
ソルクシーズの「SOLXYZ Assistant」は、入力データや機械学習データを社外に漏洩することなく活用できる社内向けAIシステムです。生成AIツールと同様に、テキストによる指示とやりとりによって、適切な情報をスムーズに取得することができます。社内業務の課題解決や効率化、働き方改革を実現します。
そんな「SOLXYZ Assistant」の開発で中心的な役割を担ったのは、ソルクシーズの事業戦略室スペシャリストとして、新技術活用の研究やプロジェクト支援を担当する南野さんです。現在は、生成AIを現場の業務に応用するための研究に注力しています。
南野さんが「SOLXYZ Assistant」の開発に着手した背景にあるのが、近年になって加速しているデジタル化の波です。
2018年に経済産業省がDXの重要性を唱えてから7年。いまや企業が国内外での競争力を維持していくためには、テクノロジーを活用した業務・ビジネスの刷新が欠かせません。ソルクシーズ社内でも、業務効率化への要求は年々高まっており、社内ナレッジの共有や業務プロセスの標準化といった取り組みを進めていました。
しかし、部門間でのナレッジ共有や、属人化した業務の標準化といった課題を、従来のシステムやワークフローで解決するのは簡単ではありません。社員ひとりひとりが必要な社内情報にスムーズにアクセスできる環境を整備することも、難しい課題のひとつです。
このような状況下で、課題解決につながる大きな可能性として浮上したのが生成AIでした。
とはいえ、生成AIには先述したような情報セキュリティやコンプライアンスの問題があり、ビジネス利用には慎重な判断・対応が求められます。企業の機密情報や個人情報をむやみに扱うと、情報漏洩などの重大なインシデントにつながりかねません。
この課題を受け、南野さんは安全かつ効率的なAI活用基盤の開発をスタート。社内の情報セキュリティ部門とも連携しながら、基盤構築から規則策定までをかなりの短期間で進めました。
開発の効率化には、AWSのBedrockなどの信頼性の高いサービス基盤と、LangChainをはじめとするOSS(オープンソースソフトウェア)の積極的な活用が役立っています。OSSは開発期間の短縮に加えて、AIシステムの品質向上にも大きく寄与しました。
オープンソースコミュニティも、さまざまな課題を克服するうえで重要な役割を果たしたソリューションです。コミュニティ内では世界中の開発者が活発に情報交換をしており、豊富な実装例・ベストプラクティスを参照できます。
たとえば、LLMの効果的な利用方法やプロンプトエンジニアリングなどの課題は、新しい技術領域ということもあり、社内だけでは解決が難しかった課題。しかしオープンソースコミュニティの知見を活用することで、本来ならかなりの工数が割かれるはずの試行錯誤を大幅に省略することができたのです。
企業のDXを加速するAIソリューション「SOLXYZ Assistant」
こうして2024年10月、「SOLXYZ Assistant」の社内リリースが実現しました。これによって、生成AIを活用した社内ナレッジの共有と業務プロセスの標準化が可能になっています。
「SOLXYZ Assistant」の最大の特徴は、セキュリティを重視した設計です。高いセキュリティ性能・信頼性が確保されたサービス基盤の採用に加え、社内プライベートネットワークでの運用と厳格なアクセス権限管理により、情報漏洩のリスクを最小化しました。
データの収集・利用については、適用範囲を最小限にとどめています。プライバシーや情報の信憑性が担保されるのはもちろん、扱う情報が限定されることで、システムの効率的な運用にもつながります。
「責任あるAI」を実現するための公平性・透明性の確保も、開発の際に重点を置いたポイント。「SOLXYZ Assistant」では、社内ナレッジなどの独自データから回答を生成した場合、回答とともに出典・参照元が明示されます。ユーザーがAIの判断材料を把握できるため、生成された情報の信頼性を吟味したうえでの活用が可能です。
AIの判断に偏りが生じないように、定期的なモニタリング・評価も実施。システムの信頼性を維持しつつ、システムの改善にもつなげます。
セキュリティや公平性・透明性とともに注力したのが、ユーザーインターフェースの使いやすさです。技術に詳しくないユーザーでも直感的に操作ができる設計にこだわったことで、実業務でスムーズにアクセスできる仕様を実現しました。
当初の予測では、主にコーディングにおける品質向上や、開発生産性の改善などの効果が期待されていた「SOLXYZ Assistant」。実際に社内で導入をスタートしてみると、開発チームの活用を通じて、コードレビューの効率化やドキュメント作成の支援といった、より広範囲でも効果が実感されています。
総務をはじめとする各部門の担当者が多くのリソースを割かれていた定型的な問い合わせも、AIが社内規定・Q&Aといった既存ドキュメントを参照することで対応可能です。担当者の負担軽減に加えて、効率的な処理にもつながりました。
部署ごとのbotに専門知識や業務フローを学習させることにより、社内用語や規則を理解させることもできます。社員同士のメール履歴を分析して、若手社員によくある質問とベテラン社員からの回答を抽出するなど、ナレッジ共有の自動化も推進していく予定です。社内に固有の情報を安全に学習させられるのも、社内向けのAIならではのメリットといえるでしょう。
そのほかにも定型業務の自動化、複雑な分析・意思決定の支援、暗黙知の可視化・共有、新規事業創出のサポート、AIを活用したOJTによる若手社員のスキルアップ、デジタルリテラシーの向上といった幅広い用途に対応。例えばバックオフィス部門の契約書チェックや、各種文書作成など、当初の想定を越えた領域でも活用が進んでいます。
社内からは「SOLXYZ Assistantを活用したことで生産性が向上した」という声が多く挙がりました。安全性・利便性を両立した「AIの民主化」により、業務の効率化はもちろん、社員の働き方や業務における思考プロセスそのものを変えるツールとして、生産性向上とイノベーションの促進が期待されています。
今後は、社内運用を通じて獲得した知見をもとに、システムのさらなる改善と機能拡張を進めていく予定です。より多様なAIサービスとの連携も進め、ユーザビリティの高いシステムとしての開発を進めていきます。
開発の最終目標は、単なる業務効率化の支援だけでなく、企業全体のDXを加速させ、新しい価値創造の基盤となるようなAIプラットフォームを実現すること。加えて、グローバル展開を見据えた多言語対応、業界特化型の特殊な知識ベースの構築など、より多様なニーズに対応できるシステムをめざします。
将来的には社内で得たノウハウをもとに、お客様向けのAIソリューションの展開も見据えています。多くの企業のDX推進に貢献するソリューションとしても進化を追求していく「SOLXYZ Assistant」に、引き続きご注目ください。
※この記事は2025年01月24日に公開した記事を再編集しています。