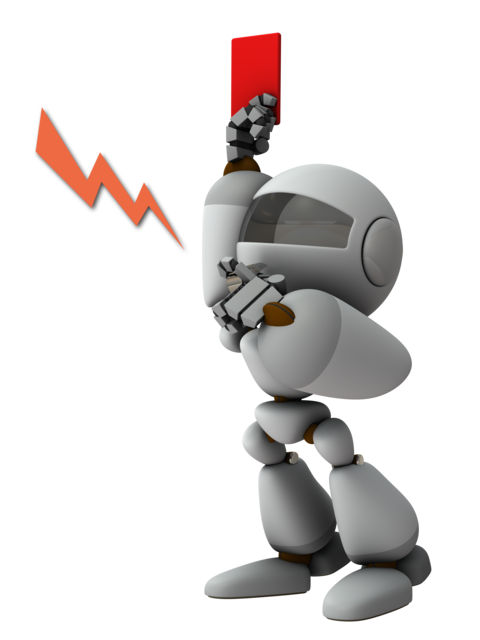【情シス野郎 チラシの裏】は、「情報処理安全確保支援士」資格を持つ情シス担当が、仕事を通して得た知識や技術を、技術面に詳しくない人でも読みやすいよう「チラシの裏」に書くかのごとく書き散らす!というシリーズです。
******
生まれついてのライオンズファンを自負するおれが一番興味を持って見るスポーツはNPB(日本プロ野球)であるが、実はサッカー好きでもある。
中学生の頃にJリーグ発足(歳バレ注意)によりサッカーブームが到来、高校生の頃にはフットサルブームが訪れ、それから10年近くにわたって同級生達と大会に参加などしていた。
自分や周囲が結婚してからはそういう機会も減ってしまったが、観戦については1993年の「ドーハの悲劇」で有名なアメリカ大会のアジア最終予選以降、日本代表の試合はほとんど欠かさず見て来た。
フランス大会アジア最終予選・韓国戦の山口選手のループシュート、ジョホールバルでの岡野選手のゴールデンゴール、そして先日のカタール大会におけるドイツ戦の堂安選手の同点ゴール。
おれが大声でガッツポーズを繰り出した日本代表(マイ)ベスト3ゴールである。
そしてこの記事を書いている時点ではカタール大会予選グループにおける日本代表は1勝1敗、決勝トーナメント進出が成るかは次のスペイン戦の結果次第という状況だ。
次戦は日本時間深夜に行われることが難点だが、幸いにも有休は充分に残っているため問題は無い。
(※記事公開時追記:日本代表はスペインに勝利して、予選グループEを1位で通過。決勝トーナメントに進出するもクロアチアにPK戦で敗れました。)
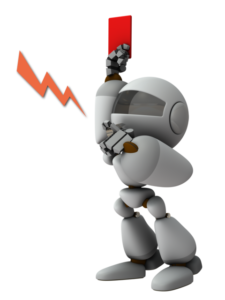
さて、このW杯カタール大会においては「AI判定」なる仕組みが導入されている。
この技術は、ボールに埋め込まれたセンサーが取得した位置データと、スタジアムに設置された多数のトラッキングカメラの選手映像データを組み合わせ、AIに分析させることでオフサイドが発生したかどうかを判定するものである。
ただしこのAI判定はそのまま採用されず、スタジアム内の特設ルームに設置されたVAR(ビデオ・アシスタント・レフリー)映像を参考にしながら最終的な判断を「人間」がくだすため、「半自動オフサイド判定技術」とネーミングされている。
この技術により、日本vsドイツ戦におけるドイツチームのゴールが検証され、結果オフサイドとして取り消された。
AIによる分析結果が判定にどこまで活かされたかは分からず、前回のロシア大会から導入されたVARだけでも事足りた感が無くもないが、少なくとも検証によりゴール判定が覆った事例である。
ところでAI技術がもたらす恩恵は、業務のオートメーション化による人件費の削減というイメージだが、今回のW杯へのAI導入を見て思ったのは、「いやむしろ人増えてるやん」ということである。
これは、この大会におけるAI導入の目的が「判定に関わる人員およびコストの削減」ではなく、「より正確な判定による公平性の確保」であることが理由だからだろう。
放送を見る限り、前述のVAR特設ルームには5名ほど(判定員と技術者?)が詰め込まれて多数の画面とにらめっこしている状況であった。
少なくともサッカーにおけるAI判定については、判定結果を改めて検証する人が新たに配置されているのは間違いない。
サッカーという競技はなかなか点が入らない、とてつもなく1点が重い競技である。ましてW杯となれば4年に1回の開催であり、1ゴールで選手やナショナルチームの歴史が大きく変わってしまう。
思い返せばマラドーナの“神の手”や、日韓大会の韓国イタリア戦のような誤審疑惑がW杯の歴史には残ってしまっている。
前回大会のVARに始まり、今回のAI導入もそれらを廃絶しようという試みの一つなのだろう。
ただし、全てのオフサイドについて厳格にファウルを取る必要がないという考えは、サッカーに詳しい人なら理解されるところだ。
得点はもちろん、攻撃側に有利な結果をもたらさなかったオフサイドプレーでいちいち試合を止めてしまうと、サッカーならではのプレーの連続性が失われ、観ている側にストレスが溜まってしまう。
つまり、流すものは流すという柔軟性も要求されているのが今回の「半自動オフサイド判定」かと推測している。「審判」というのは、人間ならではの仕事であり、だからこそ人が配置されているのだろう。
人間の仕事がAIに取って代わられる、AIが人間の知能を超える(シンギュラリティ)、などの未来予想図がよく語られる。
マニュアル化できる単純な仕事がAIに取って代わられていくことは間違いないと思われるが、柔軟性の他にも創造性、感情理解などが必要となる仕事については、当面は人間の関与が必要とされるだろう。
シンギュラリティが訪れると言われる2045年頃、どんな世界になっているか想像もつかないが、自国の代表チームとは言え、家族にウルサイと怒られるような大声で他人のゴールに歓喜する人間らしさが、一層求められる世界になっているかもしれない。