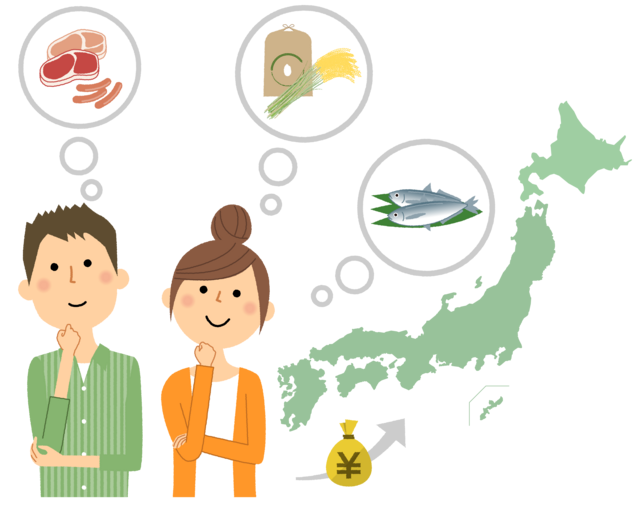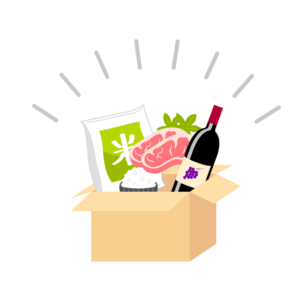過疎化が進む地方と、過密化する都市部の地域間格差の改善を図るふるさと納税。目的や意義は理解しつつも、いざ寄付をするとなると、「住民税はいくら控除されるの?」「盛り上がる返礼品は?」と、お金の話が気になります。
ポイント還元やキャンペーンが廃止される10月を目前に控え、「ソルクシーズグループの社員のふるさと納税事情」をリサーチしてみようということで、社員アンケートを実施しました。
【前編】では、ソルクシーズ、Fleekdrive、エフの社員の「始めた理由」「人気の返礼品」をリサーチ。今回の【後編】は、「ふるさと納税あるある」や、心に残るエピソードを紹介します。
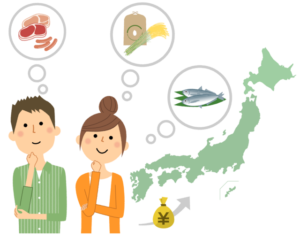
まずは、「ふるさと納税あるある」。最も多かったのは、「オーダーしすぎ」でした。日頃はお客様のサーバーやネットワークの状態をしっかり把握しているエンジニアでも、自宅の冷蔵庫の容量は盲点になりがちのようです。
「30枚の鯖が20リットルぐらいの袋で届いたのは8月で、ひとつずつラップに包んで冷凍庫に入れる間に溶け始めて大騒ぎになった」
「以前は肉類を頼むことが多かったけど、冷凍後が満杯になりがちなのでやめた」
「弁当用の食材がしまえないほど海産物を頼みすぎて、奥さんに叱られた」
「申し込む際にミスをしてしまい、同じフルーツが2倍届いて食べきれなかった」
「冷凍の返礼品が忘れた頃に到着し、そのタイミングは冷凍庫が埋まっていることが多い」
「納期がわからないとタスクが決められない」という反論もありそうですね。冷凍庫パンク事件に懲りて、ティッシュ、ペットボトルのドリンク、缶詰など日用品派に乗り換えた人も多いようです。次に多かった「締め切りぎりぎりで焦った」は、システム開発でもふるさと納税でも「あるある」です。
「新しいサイトで返礼品をオーダーしてみたら、ワンストップ申請の環境が整備されておらず、締め切りギリギリであたふたした」
「年末ぎりぎりに申し込んだため、ワンストップ申請の締め切りに間に合わず、税務署に行って確定申告することになってしまった」
「いつもやろうやろうと思って年末になってしまう」
実際に届くまで、どんなものをもらえるのかわからない返礼品の忘れられないエピソードもあるようです。
「昨今は災害が増えているので、返礼品なしの復興支援の寄付をすることもある。熊本に寄付をしたときは、『熊本城主』と書かれたカードをもらった」
「生きている毛蟹を頼んだことがある 締めるより、身をほぐすほうが大変だった」
「スイートコーンを頼んだら、その年は不作で、代わりのものを選ぶことになった」
初体験にはサプライズが付きものですが、それはさておき。ふるさと納税の魅力のひとつは、家族や友人、仕事仲間と地方の話題で盛り上がったり、喜びを分かち合ったりする機会を得られることです。ここからは、心温まるエピソードを紹介しましょう。
「返礼品のホタテで父の日のお祝いの海鮮丼を作った」
「子どもが小さいうちは生牡蠣を2人分だったけど、子どもが牡蠣のおいしさを知ってからは4人分の60個コースになった」
「昨年は両親も誘ってカニしゃぶをして、とても喜んでもらえた」
「部下の出身地の特産品を本人に勧められてから、毎年それを目当てに寄付している。人とのつながりから、縁がなかった地域を知ることができる素敵な制度だと思う」
「あるブランドの包丁を、毎年ひとつずつ増やしていくのが楽しい」
返礼品の話でテンションが上がると、ついつい「普段は買わないものが買える」などと口走ってしまいますが、「いや、買い物じゃなくて寄付のお礼です」とツッコミを入れておきましょう。
「ふるさと納税にいいたいことがあれば…」と水を向けると、「ポイント制度は残してほしかった」という意見が集まりました。「実質負担2000円で返礼品がもらえて税金も控除されるので、やらない理由がない」という声もあり、メリットを満喫してきた人にとっては、なくてはならない制度になっているようです。
その一方で、ふるさと納税の意義を実感している社員もいます。
「知らない土地のことを知るいいきっかけになる」
「納税者の意思で地方に財源が移るいい制度だと思う。それぞれの自治体が本気になって、よりよい行政サービスを提供する仕組みづくりをしてほしい」
「自分の生まれ育った場所にお礼の気持ちを込めて、毎年納税している」
実際にふるさと納税をやってみて、自分ごとになると、日本のこと、故郷のこと、今の生活のことを考えるきっかけになりそうです。以上、「ソルクシーズグループの社員のふるさと納税事情」をお届けしました。ポイント還元やキャンペーンは9月までです。この機会に、サイトをのぞいてみてはいかがでしょうか?