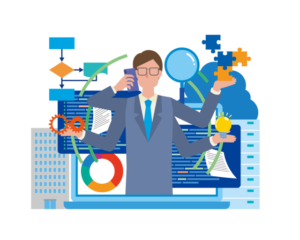「給料が安い」「長時間労働でブラック体質」「下請けの仕事ばかりで成長できない」「保守的で体質が古い」などなど、SIerがネガティブに語られている時代がありました。
しかし昨今は、「大規模なチームが必要なDXや金融・官公庁のシステム開発案件急増」「業界全体が働き方改革を推進」「人材育成の強化」「自社サービスを開発する企業が増加」「ユーザー企業の内製エンジニア不足で最注目」といった理由で、評価が高まっています。
とはいえ、SIerのなかには、サービス拡大や技術革新を推進している企業もあれば、従来型のシステム開発を続けている企業などもあります。また、SIerには4つのタイプがあり、それぞれシステムエンジニアが携われる案件の幅は異なります。
「最先端技術を武器に活躍したい」「多様なスキルを身につけられる会社に就職・転職したい」という人にとっては、気になるポイントでしょう。
そこで今回は、SIerの種類を踏まえたうえで、自分に合うSIerを見分ける方法を【前編】【後編】の2回にわたり紹介していきます。

SIerの4つのタイプ
SIerには主に4つのタイプがあり、それぞれに特色が異なります。
・メーカー系
・ユーザー系
・独立系
・外資系
「メーカー系」はPC・サーバー・ネットワーク機器といった、ハードウェアの製造会社を親会社としてもつSierです。外部から案件を受注するケースもあるものの、中心となるのは親会社のハードウェアに関連するソリューションの提案やシステム開発・ITインフラの構築です。
大規模なプロジェクトも多く、幅広い経験を積める企業が多いものの、携わる業界・分野に偏りがある企業も少なくありません。親会社との関係性や待遇は企業によって異なるため、転職を検討する際には事前のチェックが重要になります。
「ユーザー系」も同じく企業の子会社として独立したSIerです。メーカー系SIerとの違いは、親会社がハードウェア関連の企業ではなく、さまざまな領域にわたること。案件は親会社がIT関連なら自社内の開発がメインですが、それ以外の業界であれば他社からの受託が中心になるでしょう。親会社には大企業が多いため、福利厚生・労働環境がしっかりしている確率は高いといえます。
「独立系」は親会社がなくSIerとして独立している企業です。幅広い業界・取引先・技術領域の案件を受注している企業が多く、勤務形態も自由度が高い傾向があります。
ただし、会社の規模や安定性、抱えている案件、得意とする領域、労働環境、学習環境、給与などはかなりの違いがあります。待遇がよく、多様な業務を経験できる優良企業がある反面、事業収益が不安定だったり、働き方に課題を抱えていたりするケースもあります。そのため就職・転職の際には、事業の現状、社風、働き方などの見極めが非常に重要です。
「外資系」SIerは、グローバルに活躍する海外の大手IT企業が日本国内でSI事業を受注するために設立した日本法人です。海外で開発されたソフトウェアやソリューションを活用したサービスを強みとしており、特定の領域のコンサルティングを入り口として、さまざまなソリューションの導入に関わる企業も多いようです。
プロジェクトの規模が大きく給与水準が高い傾向があるものの、実力主義・能力主義の企業が多く、就職・転職の際には相応のスキルが求められるでしょう。個々人の業務範囲が細分化されているため、多様なスキル・経験が身につきにくい場合もあります。
以上がSIerの系統ごとの大まかな特徴です。自分に合う会社を探すときは個々のSIerの細かい特徴をしっかりとチェックすることが大切です。ここから先はSIerの見極め方について、チェックすべきポイントをより詳細に解説していきます。
SIerの見極め方 ①上流工程からの案件が多いか
SIerを見るポイントとしてまず挙げられるのは、「上流工程からの案件が多い」かどうかです。
要件定義・基本設計・詳細設計など、クライアントから要望をヒアリングして、具体的なシステムの全体像を決めるまでのプロセスに関われる企業は、幅広いスキルを習得することができます。予算やスケジュール、チームメンバーのアサインなど、プロジェクトマネジメントの経験を積めるのも大きなメリットです。
以前は、SIerがブラック体質になりやすいといわれていました。その最大の原因は、「多重下請け」構造です。システム開発やインフラ関連は、クライアントと契約した大手企業やその下請会社が、下流工程の設計・開発・テスト・運用・保守などを中小規模の企業に委託するケースが見られました。
基本的にはクライアントとの交渉やスケジュール調整、仕様変更依頼の受諾なども元請けの企業が担当します。
そのため、下流工程のみの下請けになると、プロジェクト全体のコントロールができません。「納期がタイトで過度な残業が発生しがち」「発注元企業のニーズを把握しづらい」「要件変更・仕様変更に振り回されやすい」「確認したい内容の返答があるまでに時間がかかる」「能力を超えた業務が求められる」など、現場のシステムエンジニアの負担は増加する傾向があります。
案件ごとの利益も、3次請け・4次請けと下層になるほど少なくなるのが一般的で、下請けがメインのSIerは経営基盤が安定しにくく、従業員の給与水準は低くなりがちです。
しかし、下流工程以外のスキル・実績が社内に蓄積されていない状態から、新たに上流工程の業務を獲得するのは簡単ではありません。優秀な人材から敬遠される可能性も高く、結果として下請けメインの状況から抜け出せずに、悪循環に陥っているSIerも少なからず存在します。
そういった環境では、エンジニアもキャリアアップに必要な上流工程の経験・スキルを学ぶ機会を得るのが難しくなります。
一方、上流工程からの案件が多い会社は、大規模Sierや経営が安定した企業が多く、専門性が高いシステムエンジニアが活躍できる場があります。
課題解決やロジカルシンキング、ビジネス的な視点に加えて、パートナー企業を含むチーム全体を束ねるプロダクトマネジメント、クライアントワークに必要な交渉・コミュニケーションなど、市場価値の高い経験・スキルが獲得しやすいのも魅力といえるでしょう。
これらの経験・能力があるシステムエンジニアは、IT業界の転職では即戦力として期待されます。平均年収が高い「プロジェクトマネージャー」「ITコンサルタント」などの職種の求人は、応募資格として上流工程の実績が求められるケースが大半です。
ただし、SIerによっては下流工程のほとんどの業務を外部に委託しているケースもあります。その場合、現場で活用できるスキルが身につかない可能性があり、実現したいキャリアによってはむしろ遠回りになるでしょう。
幅広いスキル・経験を身につけるなら、システム開発のプロセスをトータルに経験できるSIerを選ぶのがおすすめです。
なお、タイプ別に見るとメーカー系、外資系のSIerの多くは、上流工程から関わる案件が豊富な企業の比率が高いといえます。対するユーザー系、独立系は、下請けメインのSIerが多いものの、特定の業界・分野を強みとして上流工程から担う企業もあります。
SIerがどのようなプロジェクトを動かしているかは、就職・転職する企業を選ぶ際の重要なチェックポイントです。
SIerの見極め方 ②自社サービスを展開しているか
受託開発だけでなく、SIerとしてのノウハウを活かした自社サービスを展開しているかどうかも、見分けるポイントのひとつです。昨今は、社内で商品・サービスの企画・設計・開発・運用を行う「自社開発」を、受託開発との両輪で推進するSIerが増えています。
自社サービスの開発案件であれば、開発の依頼元は自社の経営陣のため、ヴィジョンを共有しながら開発を進めることができます。「コミュニケーションや連携が取りやすい」「受託開発と比べて現場の意向を反映させやすい」「成果・実績が可視化されやすい」といったあたりも自社開発案件の魅力でしょう。
受託開発は行っていない自社開発中心のIT企業もありますが、就職・転職には即戦力レベルのスキル・実績が求められるケースがほとんどです。一方、SIerは未経験OKの求人が増えており、会社によっては受託開発から自社開発に異動するチャンスもあります。
受託開発と自社開発を両方手がけている会社は、プロジェクトの上流から下流までをひと通り経験するチャンスが得られやすいのも働くメリットのひとつです。自社開発なら新しい技術の導入にチャレンジする機会も得やすく、エンジニアとしての技術力・経験・スキルが広がります。一方、経験できる領域・業務の幅は、受託開発の方が広いかもしれません。
企業にとっても、自社開発は人材育成や技術領域の拡大によって、社内リソースの底上げを図ることが可能です。自社開発で得た知見を受託開発に転用するなど、相乗効果でサービス品質の向上を推進する企業もあります。異なるビジネスモデルを展開していると、特定の要因による業績悪化のリスクが減り、経営が安定しやすいというメリットもあります。
この点は、自社開発だけを行う企業と比べたときのSIerならではの強みです。安定性の高い自社開発と、案件・人脈・技術・収益などの流動性が高い受託開発の「いいとこどり」ができるため、バランスよく企業価値を高められます。
一方、システムインテグレーションのみを継続している企業は、ビジネス環境の変化の影響を受けやすく、案件の受注が減ると「条件の良くない話も受託せざるを得ない」といった状況に陥りがちです。なかには、システムエンジニアにも追加案件の受注ノルマが課されるケースもあるようで、業務の負担が大きくなります。
これらの理由から、たとえ受託開発のプロジェクトで活躍したかったとしても、自社サービスを展開しているかどうかは重要なチェックポイントです。複数のサービスを成長させているSIerは、将来性がある企業といえる可能性が高いでしょう。
SIerの見極め方 ③専門領域があるか
上流工程、自社サービスに加えて「専門領域がある」「特定業界に強い」といったところも、SIerの見極めポイントです。まずは「専門領域」から解説します。
現在はさまざまな業界・企業で、レガシーシステムからの脱却やビッグデータの活用、DX推進が急務となっています。しかし高度なスキルを持ったIT人材が不足しており、システムエンジニアの採用はうまくいっていないようです。
特に深刻な人手不足が危惧されているのが「先端IT人材」です。「先端IT人材」とは、クラウド・IoT・AI・データサイエンス・AR/VR・自動運転・5G・セキュリティなど最先端技術のスペシャリストを指します。
これらの「先端IT技術」は、業務の自動化・効率化や、新たな付加価値の創出、スピーディーな経営判断のサポート等により、ビジネスに革新的な変化をもたらします。いまや企業が国内外の市場で競争力を維持するためには、先端IT技術の活用が欠かせません。
しかしながら、人材不足によりDX推進を内製化できない企業は、システム開発をSIerに委託せざるをえません。先端IT人材をはじめとする優秀なエンジニアを揃えられるSIerは、今後も仕事が増加していく可能性が高いでしょう。
そのようなSIerが受注する案件は、当然ながら先端IT技術が必要なものが増えていきます。在籍するシステムエンジニアにとっては、市場価値の高いスキルを身につけるチャンスが多く、キャリアアップにつながりやすいのがメリット。知識としてだけでなく、現場での実践を通して先端IT技術を習得することが可能です。
結果として、先端IT技術の実績・案件を数多く保有しているSIerには技術力・成長意欲が高いシステムエンジニアが集まりやすく、さらなる企業の成長にもつながります。SIerを選ぶ際にはどのような技術を有しているか、先端IT技術を活用した実績があるかをチェックするようにしましょう。
以上、自分に合うSIerを見分ける方法として「SIerの系統別の特徴」や「上流工程からの案件」「自社サービスの展開」「専門領域」という視点から紹介しました。【後編】でも引き続き、SIerの見分け方と特徴を解説していきます。ぜひあわせてご一読ください。
※この記事は2024年4月30日に公開した記事を再編集しています。