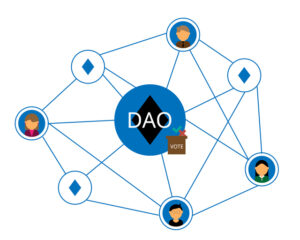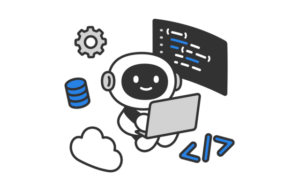「超高速大容量」「超低遅延」「多数同時接続」…5Gが2020年に日本で商用化されて以来、社会全体のデジタル化を促進する革新的なインフラとして、大きな期待を集めてきました。
しかし、サービス開始から数年が経過した今、当初の予測に反して5Gの普及は遅れ、一部の関係者からは「5Gはあまりうまくいっていない」という声も聞かれます。総務省の報告書(※1)においても「5Gは幻滅期に入っており、『5Gならでは』の実感がわかない」といった現状が指摘されているほどです。
この背景には、通信事業者が全国展開をめざしたすパブリック5Gが抱える技術的・ビジネス的な課題が存在します。その一方で、企業や自治体が限定されたエリア内で独自に5Gネットワークを構築するローカル5Gが、その弱点を補い、産業界のデジタル変革(DX)の鍵として急速に注目を集めているのが現状です。
この記事では、なぜパブリック5Gが浸透しなかったのかを分析し、ローカル5Gの持つ独自の特性とメリット、そして、この技術が日本のDXを加速させる切り札として期待される理由を詳しく解説します。

なぜ5Gは、予測通りに浸透しなかったのか
5Gは、従来の4Gと比較して通信速度が理論値で約20倍、遅延は10分の1、同時接続台数も10倍という飛躍的なスペック向上を実現しています。2時間の映画データでいえば、従来の4Gでは5分かかるところを、5Gではわずか3秒でダウンロードできるほどです。
速度ひとつとっても、これだけの差があるにもかかわらず、なぜ一般ユーザーや産業界で5Gの恩恵が実感されにくかったのでしょうか。
消費者向けサービスで「キラーコンテンツ」が不在の現実
5Gが始まった当初、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)に対応した革新的なコンテンツやデバイスが普及し、「4G=スマホ」のように5Gが新たなキラーコンテンツを生み出すと期待されていました。しかし現状は、消費者が利用する端末やアプリケーションは4G時代から大きく変化しておらず、5Gの超高速・低遅延が必須となるような魅力的なサービスが登場していません。
4Gでも動画視聴や日常的なデータ通信は十分に快適であるため、消費者が高額な5G対応端末に乗り換える動機が弱いのです。さらに、高価格や利便性の問題からAR/VRゴーグルなどの普及も限定的であり、「ユーザーにとって価値がわかりにくい」という指摘が、5G普及の大きな足かせとなっています。
既存の4Gのインフラに依存する「なんちゃって5G」の限界
国内で展開されているパブリック5Gの多くが、NSA(ノン・スタンドアローン)方式を採用しています。NSA方式は、5G専用の新しいコアネットワーク設備を構築せず、4Gの既存設備を流用しながらデータ信号のやり取りのみ5Gで行う方式です。
これにより、エリア展開のコストや時間を抑えることができる一方で、5G本来の超低遅延や多数同時接続といった特徴を最大限に発揮することができなくなっています。
この方式は、ユーザーから「4Gと速度が変わらない」「つながっているのに通信が止まる(パケ止まり)」といった不満を生む原因のひとつとなっています。このことは、通信事業者側にとっても、5Gのポテンシャルをフルに活かしたサービスを創出するモチベーション低下につながり、結果として革新的なサービスが生まれないという悪循環を引き起こしてしまったのです。
「ミリ波」の特性がもたらすエリア展開の難しさ
5Gの「超高速」を実現する鍵となるのが、28GHz帯などに割り当てられる高周波数帯のミリ波です。ミリ波は広い帯域幅を持つため高速通信が可能ですが、直進性が非常に強く、電波が届く範囲が狭いという弱点があります。
広範囲をカバーするためには、4Gよりも遥かに多い基地局を整備する必要があり、その投資コストと設置にかかる時間は膨大です。そのため、携帯通信キャリアは、投資対効果が見合わないとして、ミリ波のエリアを広げることに消極的になっているようです。多くのトラフィックが発生する駅前や繁華街といったスポット的な利用に留まっており、総務省の調査(※2)でもミリ波帯の人口カバー率はほぼ0%という実態が明らかになっています。(補足あり ※3)
ローカル5Gが持つ特性とパブリック5Gを凌駕するメリット
パブリック5Gが抱えるこれらの課題を解決し、5G本来の性能を最大限に引き出す仕組みとして登場したのがローカル5Gです。ローカル5Gは、企業や自治体が独自のエリア(工場、キャンパス、病院、農地など)に、携帯通信キャリアに依存せず5Gネットワークを構築・運用できるシステムです。
ローカル5Gは、主にSA(スタンドアローン)方式を採用し、5G専用の設備とコアネットワークを新たに構築します。これにより、4.7GHz帯のSub6や28 GHz帯のミリ波といった高周波数帯をフル活用し、5Gの三つの特長(高速大容量・超低遅延・多数同時接続)を最大限に発揮することが可能です。
さらにローカル5Gでは、利用者のニーズに合わせて上り・下りの通信速度の比率をカスタマイズできます。製造業などで監視カメラの映像やセンサーデータを大量にアップロードする場合は、上り速度に比重を置く「準同期」という設定を行うことで、データ伝送の効率を大幅に向上させることが可能です。これは、コンシューマー向けに下り速度が優先されるパブリック5Gにはない大きなメリットといえます。
外部影響を遮断し、通信の安定性とセキュリティを確保
ローカル5Gの最大の強みは、ネットワークが通信事業者の公衆網から切り離された独立回線である点にあります。この独立性により、通信事業者が提供するパブリック5Gで災害や通信障害が発生しても、自前のネットワークは外部の影響を受けることなく、安定した通信品質を維持できます。
また、ネットワークが限定されたエリア内でのみ構築されるため、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えてセキュリティを強化できるのも、機密性の高いデータを扱う企業にとっては重要なメリットです。公衆回線を利用するパブリック5Gとは一線を画す高い信頼性と安全性が確保されるのです。
4Gの約10倍の機能性がもたらす「産業変革」
ローカル5Gが提供する「超高速通信(eMBB)」「超高信頼・超低遅延(URLLC)」「多数同時接続(mMTC)」という3つの特徴は、産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)に不可欠な機能性を提供します。
パブリック5Gの普及が遅れる中で、ローカル5Gが産業の現場で急速に導入され、注目度を高めているのは、その技術特性がDX時代の企業ニーズと完全に合致しているからです。
5Gの特性であるミリ波は、電波が届く範囲が狭く、障害物に弱いという弱点があります。しかし、この弱点は裏を返せば、「限定されたエリア」では力を最大限に発揮できるという強みになります。工場、倉庫、病院、大学キャンパスといった閉鎖的で比較的狭いエリアでは、基地局を効率的に配置でき、ミリ波の持つ超高速・超低遅延のポテンシャルをフルに引き出せます。
産業利用の現場では、数万台のセンサーやロボットが接続されるスマートファクトリー化、高精細な映像を用いた遠隔医療、無人運転によるスマート農業など、通信の安定性や遅延が製品の品質や人命に直結するシビアな環境が求められます。
ローカル5Gは、これらの高信頼性とセキュリティが要求されるプライベートな通信ニーズに最適解を提供し、DX推進の基盤となりつつあるといえます。
遠隔操作・自動化を実現するユースケースの広がり
ローカル5Gは、さまざまな産業で成果を生み出しています。製造・物流業界では、カメラやセンサーで集めた膨大なデータをAIがリアルタイムで分析し、機器トラブルの予兆を検知する予知保全が行われています。この仕組みは、ロボットやドローンの自動制御により、危険な場所での作業員事故防止にも貢献します。
建設業界の事例として挙げられるのは、港にあるコンテナターミナルにおけるクレーンの遠隔操作やリアルタイム映像伝送です。これらの導入により、大幅なコスト削減が見込まれています。
医療業界では、CT画像などの大容量の情報を瞬時に共有する技術が、遠隔診療やロボットによる遠隔手術に活用できます。VRゴーグルを利用したリアルタイムの遠隔会議の実証実験なども行われており、病院が少ない遠隔地とのコミュニケーションの質も向上しています。
ローカル5Gは、単なる通信速度の向上に留まらず、「遠隔」「自動化」「無人化」という新たな価値創造を実現するインフラとして機能しているといえるでしょう。
5G/6G時代の通信インフラ構築とコスト削減への貢献
ローカル5Gの急速な普及は、日本のデジタル変革(DX)を加速させるだけでなく、次世代通信インフラの構築に対する考え方そのものを変えつつあります。従来のパブリック5Gは、通信事業者が全国津々浦々をカバーするために巨額の設備投資を行う「面」の戦略が中心でした。しかし前述の通り、高周波数帯のミリ波が抱える電波伝搬の難しさや、利用者数の少ない地域での採算性の問題から、この戦略には限界が見えています。
この状況をふまえて、ローカル5Gがもたらす「必要な場所に必要な性能のネットワークを構築する」という「点」「局所」の戦略が浮上しています。企業や自治体が自前でネットワークを構築するローカル5Gは、インフラ整備が遅れる地域や、山間部など電波が届きにくい場所でも、早期に5Gの恩恵を受けられるようにしてくれます。これは、日本の地域社会や産業のデジタル格差を埋める上で、極めて重要な役割です。
さらに、インフラ構築のコストを抑えるための取り組みも始まっています。5Gは4Gよりも多くの基地局が必要となるため、基地局の設備や設置場所を複数の通信会社やローカル5G事業者が共同で利用する基地局シェアリングが注目されています。
特に都市部で基地局設置場所の確保が困難な状況においては、通信事業者にとって設置コストの削減、効率的なエリア展開につながる大きなメリットがあります。
ローカル5Gの導入には、現状ではネットワーク構築に数千万から数億円の初期コストがかかり、電波利用料も発生するというデメリットが存在します。しかし、この初期投資は、超低遅延・高信頼性を基盤としたDXソリューションによって、長期的な生産性向上、人件費削減、品質管理の徹底といった形で回収が見込めます。
例えば、スマートファクトリー化によって製造ラインの異常検知をリアルタイムで行えれば、重大な機械トラブルを未然に防ぎ、操業停止による損失を回避できます。このようにローカル5Gは、単なる通信手段ではなく、企業競争力を高めるための戦略的投資として位置づけられ始めているのです。
さらに、2030年頃に登場が予測される「Beyond 5G(6G)」の議論においても、ローカル5Gが示した「エリアを限定し、ニーズに最適化する」というアプローチは大きな示唆を与えています。
通信業界では、従来の「世代(G)の更新=電波の高度化(より高い周波数を使う)」という単線的な進歩史観が揺らぎ、「5G以降は、テラヘルツ波利用などの電波高度化だけでなく、人工衛星との直接通信や空飛ぶ基地局など、電波の高度化以外の要素も含む」という「Beyond 5G」という呼称が使われ始めています。
Beyond 5G 時代において、ローカル5Gは、パブリックネットワークではカバーできない特定の高信頼性・高機能性ニーズを満たすために不可欠なインフラとして存在感を高めていくでしょう。パブリック5Gが広域の一般接続を担う「マクロな通信基盤」となる一方で、ローカル5Gは、産業の心臓部を守る「ミクロで高性能な通信インフラ」として、日本のDXと次世代通信の進化を力強く支える存在となることが期待されています。
出典
※1
デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会5G普及のためのインフラ整備推進WG報告書(案)概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000958608.pdf
※2
5G ビジネスデザインと新たな携帯電話用周波数の割当方式の検討について
総務省
https://www.fmmc.or.jp/Portals/0/resources/ann/pdf/news/fmmcseminar_22w.pdf
※3
『有効利用評価方針の改定の考え方及び改定内容等』(資料27-3)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000953450.pdf
「ミリ波は、スポット的な利用が前提となることから、エリアカバレッジ(人口カバー率、面積カバー率、基盤展開率)の観点からの評価は行わない。」と記載あり
※この記事は2025年8月15日に公開した記事を再編集しています。