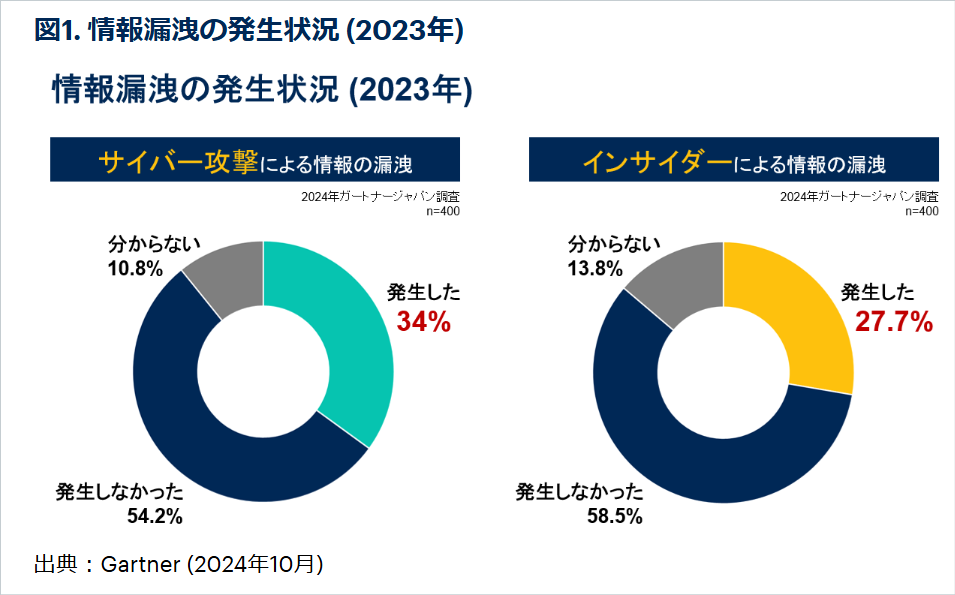高いカスタマイズ性能により、業界ごとのニーズ・環境に柔軟に適合する「インダストリー・クラウド・プラットフォーム(ICP)」。ガートナージャパンが発表した「2024年の戦略的テクノロジーのトップ・トレンド」にも取り上げられるなど、注目度が高まっているクラウドソリューションです。
北米と欧州の企業を対象にした調査では、39%がICPの採用に着手していると回答しました。またそのほかの14%が試験的導入を実施、17%が2026年までの導入を検討しています。
ガートナージャパンは、「ICPを利用する企業が、2023年の15%未満から2027年には70%にまで増加する」と予測しており、今後は国内の需要も上昇していく可能性が高いといえるでしょう。
この記事では、ICPについて具体的な特徴や活用メリット、業界ごとの導入事例、導入方法などを網羅的に解説。クラウド環境を最適化することで「業界固有の課題を解決したい」「ビジネスの成長を加速させたい」とお考えの方は、ぜひご一読ください。

インダストリープラットフォーム(ICP)とは?
昨今は多くの企業がデータセンターをクラウドに移行することで、データ管理・活用の効率化やコスト削減を実現しています。CRM(顧客関係管理)、ERP(基幹システム)、会計クラウドなど、個別具体の業務に特化したクラウドサービスも普及しており、企業の生産性向上に大きく貢献しました。
日本企業がレガシーシステムの刷新や業務・サービスのデジタル化を実現して、国際的な競争力を取り戻すためにも、いまやクラウドサービスは欠かせない存在といえるでしょう。
そんな中でICPが注目されはじめた背景には、従来の汎用的なクラウドサービスでは業界固有のビジネスフローやデータ活用、コンプライアンスなどの細かな要求に対応しきれないという課題がありました。
当然ながら、IT業界・金融業界・製造業界・小売業・医療業界では、業務内容も扱うデータの種類もバラバラなため、クラウドに求められる機能・性能はそれぞれに異なります。しかし従来型のクラウドサービスの多くは、特定の業界での利用が想定されているわけではありません。
解決策のひとつは、複数のサービスを組み合わせて、個々のクラウドサービスの不足を補うこと。ただし、そのためにはクラウドサービスを導入・連携・管理するための高度な知識・スキルが必要です。サービスの組み合わせによっては機能が重複するなど、余計な費用がかさんでしまう場合もあるでしょう。管理のための手間やコストも、サービスの数が多くなるほど増大していきます。

また、データの保護・保持に規制がある業界、利用できるソフトウェアに制限がある業界など、そもそも既存のパブリッククラウドでは要件をクリアできないケースも存在します。建築現場や農場、石油リグ※ など、インターネットへの常時接続が難しい環境でのテクノロジー活用も、従来のクラウドサービスではカバーが難しい領域です。
※石油リグ:海底から石油や天然ガスを掘削・生産するために海上に設置される規模の大きい海洋構造物
これらの課題を解決するため、クラウド市場の成熟にともなって生まれたソリューションがICPです。
ICPはパブリッククラウドのインフラをベースに、異なるクラウドサービス・機能を組み合わせることで、これらのニーズを満たす「業界特化型」のアプリケーションやデータベース、セキュリティ体制を構築。それぞれの業界標準の業務プロセスや規制要件に最適化した、効率的で利便性・堅牢性に優れたクラウド環境を実現できます。
現在はAWSやGoogle Cloud Platform、Microsoft Azureといった大手パブリッククラウド事業者がICP開発に着手。Athenahealth、SAP、Veeva Systems、Shopifyなど各業界に特化したICPを提供する事業者も増加しており、業界固有の課題解決に貢献しています。
ICPを活用するメリット
企業がICPを活用するメリットは、なんといっても自社のワークフローにマッチしたクラウド環境を簡単に実現できることです。
ICPは業界のビジネスモデルや業務プロセス、課題ごとに最適化された過不足のないサービスパッケージを提供しています。各業界の企業はこのサービスパッケージを採用すれば、クラウド業務システム稼働までに必要な時間を大幅に削減できます。
業界に特化したサービスのため、その後のクラウド上での業務遂行もスムーズ。結果として、導入企業は生産性の向上やヒューマンエラーの軽減など、さまざまな成果が得られるでしょう。
業界別のデータファブリック(異なる場所にある関連データを連携し一元管理する概念)を採用できるため、ビッグデータの収集・管理・分析を最適化できるのもメリットのひとつです。

セキュリティに特化した仕組みで、安心安全なデータの活用が可能。顧客ニーズの分析や業務データの蓄積により、より効果的な経営判断が行えるようになります。パブリッククラウドのデータ容量内で利用を制限されることもありません。ICPは基盤となるサーバーやストレージのスケーラビリティが高いため、状況に応じて臨機応変に機能を拡張・変更・削除することが可能です。
ベンダーが提供する各種サービスや、監視・管理機能、各種アプリケーションの追加も、サービスカタログから必要なものを選ぶだけ。利用状況に応じて不要になった機能を停止するといった操作も容易です。急速な外部環境の変化にもフレキシブルに対応できるのは、ICPの大きな強みといえます。
AI・IoT・エッジコンピューティングといった先端テクノロジーのテスト・導入を、迅速かつ低コストで行えるようになるのもメリットでしょう。膨大なデータを分析できるアナリティクスサービスを追加すれば、効果的なマーケティング戦略も遂行しやすくなります。新規事業もよりスピーディーに展開できるようになるなど、さまざまなシーンでビジネス変革のハードルが下がるため、継続的な改善を繰り返しながらアダプティブに経営戦略を推進できます。
また、業界固有の規制や厳しいコンプライアンスにも、ICPなら柔軟に対応可能です。地域に応じて個人情報・機密情報などのデータ利用を制限するといったカスタマイズもできるため、EUが定めるデータ保護規則「GDPR」などへの対処もしやすくなるでしょう。
「GDPR」はEU内の国民の個人情報を、合意なくEU外に転送することを禁止する規則です。ICPならデータの利用地域をEU内に制限することで、この制限に抵触せずに、ストレスのないデータの取り扱いが可能になります。
もちろん、従来のクラウド同様に、運用や保守、災害時の安全対策はプロバイダーに任せることができるので、システム構築・維持の手間もかかりません。加えて複数のサービスの監視・管理が一元化されるため、セキュリティ設定やシステム連携などにかかる業務負荷が大幅に削減できます。
従量課金制のソリューションで、コストパフォーマンスが高いのも魅力です。初期費用がほとんどかからず、ランニングコストもサービスを利用した分のみ。目的に応じて複数のサービスを導入する必要もなく、時期ごとの業務状況に応じて運用費用を最小限に抑えることができるでしょう。
ICPの業界別の導入事例
このようにさまざまな強みがあるICPですが、各業界にもたらす具体的なメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは業界別の導入事例について、詳しく解説していきます。
最初に取り上げるのは「医療業界」。数年前からクラウドサービスの導入が活発化している業界です。しかし、患者のカルテ・来院状況・診療記録といった個人情報に関わる領域だけは、データ保護規制の問題からこれまでクラウドへのシフトが困難でした。
ICPなら、安全な情報の保管場所と管理体制を確保することでこの課題を解決できます。これによりビッグデータの活用が進めば、治療を含む医療サービス全体の品質向上につながる可能性もあるでしょう。
同じく個人情報保護やデータ活用の観点から、ICPに注目が集まっているのが「金融業界」。口座情報や顧客情報をリアルタイムに集計する業務では、安全性の高いクラウド環境が重宝されるでしょう。
保険領域ではIoT技術を駆使した運転データの収集により、ドライバーの潜在リスクを評価するソリューションも注目されており、ICPがその実現に一役買う可能性があります。また、証券・クレジット・金融商品などは頻繁にルール改正が行われる領域でもあるため、柔軟性の高いICPとの相性は抜群です。
「小売業」もビッグデータの活用が売上を大きく左右する領域です。国内外の多くの小売企業が、データのストレージや収集手段を拡大するため、クラウドサービスへの投資を拡大しています。

ICPの活用により、顧客の購買情報・嗜好情報をはじめとする膨大なデータをセキュアに効率的に分析できる体制が整えば、より顧客満足度の高い販売戦略を打ち立てることができるでしょう。商品の入出荷や流通経路、運搬状況、店舗在庫、販売数などに関する情報をリアルタイムに把握して適切なタイミングで商品補充を行う小売管理システムも、高い精度で実現できます。
「製造業」でも、部品・材料の入荷や工場の製造ラインに使われるシステム、製品の配送システム、販売のためのシステムなどをクラウドに移行する動きが進んでいます。
ICPの導入によってクラウド上で生産計画から在庫管理・品質管理までの業務プロセスをまとめて実施・管理できれば、さらなる業務効率化を図れるでしょう。AI・IoTなどを活用したスマートファクトリーも、低コストかつスムーズに実現可能です。
現在データ活用が進んでいる「農業」でも、ICPがもたらす恩恵は小さくありません。センサーが収集する機械や土壌・作物・動物などのさまざまなデータを、クラウドサービスが処理。作物の育成やその環境に関する新たな知見を生み出すことができるようになります。
ICPの導入方法
社内の既存の機能やシステムをそのまま置き換えるだけでは、ICPの強みを最大限に活かすことはできません。ICPを効果的に導入するためには、事前の詳細な「戦略策定」が大切になります。
まずは自社で活用しているシステムやサービス、業務プロセス、解決が必要な課題、満たすべき要件などの棚卸しをして、構築すべきクラウド環境を具体化しましょう。
このプロセスは、自社の現状を再確認する契機にもなりえます。業務やシステム環境にどのような無駄・機能の不足・リスクがあるのかを把握することで、業務改善やリソース配分の方向性を決定。重要性がそこまで高くない業務をアウトソースして、その分のリソースをコア業務に注力できるようになれば、競争優位性の向上をめざせます。

さらに、生産性の向上やコスト削減にとどまらない攻めの施策が実現できれば、他社との差別化により、さらなる企業価値向上を見込めるでしょう。ICPによってどのような付加価値を獲得できるのか、自社のサービスやビジネスモデルにどのような変革をもたらせるのかを追及していく姿勢が重要です。
構築したいクラウド環境の方向性が決まったら、いよいよベンダーを選定します。提供サービスや機能・導入事例などをチェックして、自社の要件に最もマッチしたベンダーを選びましょう。
ICPは環境を構築した後でも、柔軟に機能を追加・削除できるため、一度にすべてをクラウド化する必要はありません。予算に無理がない範囲で、重要度の高い施策から少しずつ着手していくことが可能です。
ただし導入には注意点も。ICPは業界固有の業務プロセス・ニーズに最適化している反面、一部機能に関しては、柔軟なカスタマイズや変更ができない場合があります。そのため企業独自の要件がある場合には、そのニーズをかなえられない可能性もゼロではありません。
適切な導入には、経営戦略やクラウドに関する知識も不可欠です。社内に知見がない場合には、SIサービスやITコンサルなど、外部リソースの活用も検討してみましょう。
以上、ICPの特徴や活用メリット、業界別の成功事例、導入方法について解説しました。業務プロセスのクラウド移行を進めたいとお考えの方は、ぜひ業界に最適化されたICPの導入を検討してみてください。
※この記事は2024年7月24日に公開した記事を再編集しています。