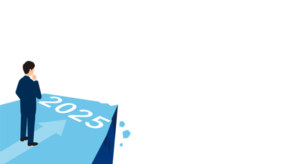クラウドやWebサイトの制作・管理サービスが進化するなかで、サーバーも多様化が進んでいます。顧客のシステムの保守やサイト運用に携わりながらも、最新情報を追いきれていないという人も多いのではないでしょうか。
今回は【前編】【後編】の2回にわたり、サーバーの仕組みや種類、トレンド、最新トピックスについて詳しく解説していきます。
サーバーの仕組みと種類
まずはあらためて、サーバーの仕組み・種類についておさらいしておきましょう。
「サーバー(Server)」はサービスやデータ、サイトなどの多種多様な情報を保存するコンピュータです。ただ情報を保存するだけでなく、インターネットなどのネットワークを通じて、クライアント(端末や利用者)からの要求にマッチした情報を提供します。

サービスの提供は「レスポンス」とも呼ばれ、サーバーごとにインストールされたOS、ミドルウェア、アプリケーションによって実行されます。
サーバーの物理的な構成要素はマザーボード、CPU、メモリ、HDD、電源など、一般的なパソコンとさほど大きな違いがありません。ただし個人向けのパソコンと比べると、耐久性やスペック、セキュリティ性能などはかなり高く設計されています。
IT領域ではあらゆるシステムにこのサーバーが使われており、現代社会の重要なインフラのひとつといえるでしょう。
サーバーは保存・提供する情報の種類や用途に応じて分類されています。主要なサーバーの種類は下記のとおりです。
・Webサイトを表示するWebサーバー
・WebサイトにアクセスするためのDNSサーバー
・データ通信を暗号化するSSLサーバー
・メールの送受信に必要なメールサーバー
・データの共有・使用を行うファイルサーバー
・データベースを参照するDBサーバー
・プログラムを動作させるアプリケーションサーバー
・サーバーとファイルの送受信をするFTPサーバー
・リソース情報を管理するディレクトリサーバー
・システム内のログを管理するSyslogサーバー
「Webサーバー」は、ブラウザ上にWebページや画像などのコンテンツ、サービスを表示させるためのサーバーです。企業や個人がホームページやブログを立ち上げる場合にも、Webサーバーの利用は欠かせません。この記事の【後編】では、シェアが高いWebサーバーソフトウェアも紹介していきます。
WebサイトのIPアドレスとドメイン名を紐づける「DNSサーバー」も、Webサイトへの接続時に必要なサーバーです。IPアドレスはネットワーク上の住所のようなもので、最大12桁のシンプルな数列で示されます。ドメイン名はこのIPアドレスを人間が理解しやすい名前に変換したものです。
「SSLサーバー」は通信データを盗み見やなりすまし、データ改ざんなどから防止するための機能を果たします。
「DBサーバー」はデータの保存・管理に特化したサーバー。企業が顧客情報などを格納するのに活用します。大量のデータの一元管理だけでなく、DX推進のためのデータ活用でも大切な役割を果たすシステムといえるでしょう。
ほかにメール、アプリケーション、ソフトウェアといった各種サービスを動作させるうえでも、サーバーの役割は重要です。また企業を支える基盤システムのなかでも、サーバーは中心的な役割を果たしています。
また、サーバーを対応範囲で分類すると、2つに分かれます。「アプライアンスサーバー」は特定の用途に向けて、特定の機能を提供するサーバーです。たとえばメーカーにハードウェアを特注すれば、自社に最適化した専用のサーバー環境を構築できます。
「汎用サーバー」は、文字通り幅広い用途に使える汎用的なサーバー。OSやソフトウェアをインストールすることで、1台のハードウェアに複数の機能をもたせることが可能です。
サーバーのハードウェアの種類
サーバーのハードウェアには「タワー型」「ラックマウント型」「ブレード型」の3つがあり、それぞれ必要となる設置スペースや消費電力・費用などが異なります。
「タワー型」は直方体のデスクトップパソコンと同様の形状をしたサーバー。物理的スペースが限られた場所に設置でき、専用のサーバールームを用意する必要がありません。ほかのサーバーと比べると導入費用が安く済むのもメリットです。
増設・拡張に不向きで基本的には単体で使用されるため、小規模なシステムで構わないときや、スモールスタートをしたい場面で選ばれます。相応の規模を実現したい場合には、残り2つのハードウェアを選ぶ必要があるでしょう。
「ラックマウント型」は「ラック型」とも呼ばれ、サーバーラックという縦長の筐体に、サーバーのハードウェアや関連部品、冷却用のファンなどをひとつひとつ積み重ねる形で格納する形式です。
複数のサーバーを組み合わせて利用できるのが特徴で、中〜大規模なシステムで採用されます。サーバーラックに鍵をかけることもできるため、セキュリティが堅牢なのも魅力。物理故障のリスクも最小限に抑えられるでしょう。カスタマイズパーツも豊富です。
ただし相応の規模を確保するためにはスペースが必要。運用コスト・消費電力もほかのサーバーと比べて高くなりがちです。
「ブレード型」は「ブレード」と呼ばれる薄くて細長い形状の筐体に、サーバーのハードウェアや周辺機器などを搭載する形式です。
この筐体を複数組み合わせて構成するのが一般的。その場合にはブレードシャーシと呼ばれる筐体にまとめて格納して、ブレードシャーシから電力・ケーブルなどを供給します。増設もブレードシャーシに新たな筐体を差し込むだけなので簡単です。
大規模なシステムを実現しやすいうえに、ラックマウント型と比べてサイズ感が小さく、構築・管理が必要になる設備や部品がシンプルなのも特徴。ただしほかの型と比べてコストが高くつくのがデメリットです。
物理サーバーと仮想サーバー
サーバーの設置環境は、「物理サーバー」「仮想サーバー」の2種類に大別されます。
物理サーバーはその名の通り、物理的に存在するサーバーがそれぞれの用途に応じて機能している状態です。
たとえば「専用サーバー」は、ハードウェアを企業または個人が占有するサーバーのあり方です。高度な性能や自由度の高いカスタマイズ性、堅牢性の高い環境を実現できるのが特徴です。ただし構築や管理には専門的な知識が必要になり、相応の費用も必要になります。
ハードウェアを複数のユーザーで共有するサービスは「共用サーバー」「レンタルサーバー」などと呼ばれます。環境の構築・管理はサービスを提供している会社が行うためサーバー関連の高度なスキル・知識がなくても利用でき、コストパフォーマンスも高いのが特徴です。スペックや容量の変更がしやすいのも、専用サーバーにはないメリットといえます。
対して仮想サーバーは、仮想化ソフトウェアを使って1台の物理サーバーを複数の仮想的なサーバーに分割して稼働させる仕組みです。物理サーバーとは一軒家とマンションのような違いがあり、ハードウェアを共有しているにもかかわらず、仮想化されたサーバー内ではそれぞれに異なる用途での活用できます。大規模なシステムのリソースが余剰なく分配できることから、より効率的なサーバー環境といえるでしょう。
「VPS(Virtual Private Server)」は、代表的な仮想サーバーのひとつです。サーバー内に利用者ごとの環境を構築して、管理者権限とともに提供します。
利用者は権限の範囲内ではあるものの、任意の設定をしたり、特定のアプリケーションをインストールしたりと、専用サーバーと似たような感覚でサーバーを活用することが可能です。ただし使いこなすためにはサーバー関連の基本的な知識が必要になります。
複数のユーザーが共有する「クラウドサーバー」も、仮想サーバーの代表例といえるでしょう。クラウドサーバーはサービスを提供するベンダー企業が非常に規模の大きいシステム基盤のうえに構築したサーバー環境。容量・用途・処理速度などの柔軟性・拡張性の高さが特徴です。
クラウドサーバーとハイブリッドクラウド
もともと企業のサーバーは、自社にネットワーク機器やサーバーを収納するデータセンターを設置してシステムを運用する「オンプレミス」が主流でした。前述の分類でいえば、「専用サーバー」に該当する運用手法です。
しかし昨今は、クラウドの普及により、外部のサーバーを利用するケースが増加しています。
クラウドサーバーなら物理的なスペースが不要なうえに、運用に必要なコスト・人員を大幅に削減でき、より手軽かつ柔軟に最適なサーバー環境を構築することが可能です。異なる地域にまたがる複数台のコンピュータで分散管理されているため、自然災害などによる障害・トラブルに強いのも魅力です。
さらに従量課金制の料金制度を採用しているサービスが多く、必要な容量・機能に合わせてその都度その都度でスケールアップ・スケールダウンを行うなど、使い勝手のよさも従来のサーバーにはなかった強みといえるでしょう。
企業がDXを推進していくうえでは、レガシーシステムの刷新や、全社横断的なデータ活用の体制づくりが不可欠です。しかしゼロから環境を構築しようとすると、膨大な時間・労力・コストがかかります。
その点、クラウドであればスピーディーかつ最低限のコストで、新たなシステムやデータセンターの構築が可能です。また、アプリケーションや先端技術の活用基盤も柔軟に立ち上げられるため、新サービスの展開を迅速化しやすく、競争優位性の向上がはかれるでしょう。
ただし、データを外部システムで保管するクラウドサーバーは、オンプレミスのサーバーと比べて、セキュリティ面での不安が指摘されるケースが多いようです。自社にインフラを構築するオンプレミスは、セキュリティ対策がしやすく、重要な顧客データ・機密情報をより安全に保管できるのがメリットです。
加えて、業界・企業を問わず幅広いユーザーが想定されるクラウドでは、固有の状況に対応できない場合もあるでしょう。既存の社内システムとの連携ができず、オンプレミスに頼らざるを得ないというシチュエーションも珍しくありません。
DX推進が活発になってからは、クラウドサービスを活用しつつも、基幹システムや機密情報の管理などに堅牢なオンプレミスを取り入れる「ハイブリッドクラウド」を採用する企業が増えてきています。
ハイブリッドクラウドなら、クラウドサーバーと物理サーバーのデメリットを補い合うことが可能です。うまくはまれば、コスト面でも無駄なく運用ができるでしょう。
企業がハイブリッドクラウドの強みを最大限に生かすには、活用するサーバーの適切な役割分担と、比重の調整がポイントになります。複数のサーバーを組み合わせて活用するため、システムの構成・管理はどうしても複雑になりやすいのが難点。コスト計算も複雑化しやすく、慣れていないと余計な費用がかかってしまう場合もあります。
ちなみに、ハイブリッドクラウドによく似た言葉で「マルチクラウド」というものもあります。マルチクラウドは複数のクラウドサーバーを利用するサーバーのあり方で、物理サーバーは含まれません。
能動型のサーバー
昨今はクライアントの要求に応じる「受動型」のサーバーのほかに、サーバーが自動で指示出しや異常検知を行う「能動型」のサーバーも注目されています。
たとえば「SNMP(Simple Network Management Protocol)サーバー」は、ルーターやスイッチなど、ネットワーク機器を監視・制御するためのサーバーです
ほかにもシステムの監視・制御、BPMS(ビジネス・プロセス・マネジメント・システム)に加え、AI、RPA(Robotic Process Automation)、IoT、ビッグデータ、クラウドといった先端IT技術の領域で、能動型のサーバーが活用されています。
これらのサーバーの仕組みに精通することで、適切なIT環境の構築やDXをより柔軟に推進できるようになるでしょう。
以上、【前編】ではサーバーの仕組みや種類を踏まえたうえで、クラウドサーバー、ハイブリッドクラウド、能動型のサーバーなどのトレンドについても解説しました。
【後編】でも、引き続きサーバーのトレンド情報をレポートしていきます。サーバー環境の構築に役立つ最新トピックスも紹介するので、ぜひご一読ください。
※この記事は2024年01月30日に公開した記事を再編集しています。