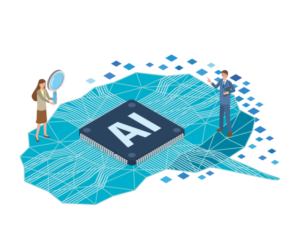【情シス野郎 チラシの裏】は、「情報処理安全確保支援士」資格を持つ情シス担当が、仕事や自らの体験を通して得た知識や技術を、技術面に詳しくない人でも読みやすいよう「チラシの裏」に書くかのごとく書き散らす!というシリーズです。
******
7月30日の日本時間朝、カムチャツカ半島付近で大地震が発生した。
おれは海のない県に住んでいるため、今回の警報では特に何もしなかったが、日本でも広範囲にわたって津波警報が出され、200万人弱の人たちが避難し、津波による人的被害はなかったと報道されている。
2011年の東日本大震災時の津波に対する避難者は数十万人と言われている。
今回は朝の早い時間に発生した、ちょっと離れた場所での地震にも関わらず、避難者の数が大きく増えているところを見ると、特に沿岸部地域の方々には、「警報が出たら、とにかく避難」ということが教訓として浸透していると推測する。
なお津波警報は太平洋沿岸諸国で広く出され、合計で300万人以上が避難したとのことだ。

どこで地震が発生し、どの程度の津波がいつ頃に到達するのか。
このような情報は、太平洋地域においては、PTWC「太平洋津波警報センター」から気象庁に自動で即時共有される。
気象庁はPTWCからの情報を解析すると同時に、自国の観測網と照らし合わせ、必要に応じて警報や注意報を出す、という流れのようだ。
ちなみに、PTWCのTはそのままTsunamiのTである。
1946年にハワイを襲った大波を日系人が津波と言ったことで、Tsunamiは世界共通語として広がった。言葉が示す現象はよくないことだが、母国語がそのまま通じるのは、ちょっと誇らしい気がしてしまう。
日本における「海底地震津波観測網」には3種類ある。
1つは、S-netと呼ばれる、日本海溝からその内側に房総沖から釧路沖まで敷き詰められた装置と、それらを繋ぐケーブルである。ケーブル全長は5500kmにも及ぶ。
装置は地震計と水圧計を一体化しており、リアルタイムで観測データを取得するとのことだ。
2つ目は、DONETと呼ばれる、三重、和歌山、四国の南海域、南海トラフ付近に張り巡らされた観測網である。
3つ目は、N-netで南海トラフ地震の想定震源域のうち、DONET設置域のさらに西側である高知県沖~日向灘に設置されている観測網だ。この観測網には拡張用の分岐装置が備えられていて、将来新たな観測装置を繋ぐことが出来るとのこと。
3つともに防災科学技術研究所の地震津波火山観測研究所により運用されている。
ところで、S-netによる検知から、スマホで緊急地震速報が鳴るまでのリードタイムは10秒程度と言われている。
緊急地震速報に使われる通信方式は通常のデータ通信とは異なり、スマホが常に受信している基地局からの電波に乗せて送られる。そのため、極端に電波が悪いなどの特殊な状況でない限り、超速で受信される仕組みとなっている。
ちなみに、どうしてもあのけたたましい音が心臓に悪いという方は、iPhoneでもandroidでも設定でオフに出来る。お勧めはしないが。
歴史を紐解けば、紀元前より巨大津波は三陸と南海トラフで繰り返されている。
「次の」南海トラフ地震はいつくるかは分からないが、必ずいつかは来るものである。
日本は海に囲まれており、地震による直接被害よりも、津波による二次被害の方が甚大になることは先の震災が示す通りだ。
しかし幸いにも技術の発展によって、津波到達前に逃げるだけの情報を得ることが出来る状況である。我々も気持ちの備えと、避難場所や家族らとの連絡方法などの確認は怠らないよう心掛けたい。
※参照サイト※
「海底地震津波観測網」https://www.seafloor.bosai.go.jp/S-net/